オススメ記事
-

コラーゲンの産生促進剤として特許取得!資生堂発「コケモモ+アムラ果実」成分とは
ハリ不足やたるみといった肌悩みの解決策として、コラーゲン配合の美容ドリンクを飲む女性は多いと思います。そのコラーゲンの産生を促進する成分があることはご存知ですか?資生堂が開発し、特許を取得したのは、コケモモとアムラという2つの果実を原料にした「コラーゲン産生促進剤」!これがどのような成分なのかを見ていきましょう。
-

コラーゲン摂取に新たな見解!量だけでなく、種類や相乗効果が期待できる成分を上手に活用しよう!
美容にいい栄養素として知名度のあるコラーゲン。しかし「とりあえずたくさん摂ろう」「摂取したところで意味があるの?」と、コラーゲンを飲むことに対する見解は様々ですよね。ここではコラーゲンを飲むことで期待できる効果や、一緒に摂取することで肌への美容効果が高まる、他成分についてご紹介します。
-

元に戻らない日焼けを戻す方法はある?肌を白くするおすすめの美白ケア
日焼けで黒くなった肌は、できるだけ早く元の色に戻したいと思います。しかし、さらなる日焼けや加齢などさまざまな原因で、肌の色が戻るまでに時間がかかる場合もあります。日焼けした肌の色を戻すには、どのような方法があるのでしょうか。
-

日焼けした肌の色が戻らない!元に戻るまでの期間と原因・対処法
日焼けした後、肌の色が戻らないというお悩みは、意外と多いかもしれません。日焼けの跡がいつまでも残っていると目立つし、着られる服も限られてくるので早く戻したいと思いませんか。日焼け後の肌の色が戻らない原因や対処法を解説します。
スキンケア講座
-
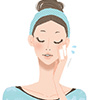
スキンケア基礎講座
美を目指すすべての方に!お肌にまつわる基礎知識から豆知識までを、ドクター監修の読みやすい記事で網羅。気になること、わからないこと、ここで見つかります。
-

メイク講座
メイクの基礎知識をはじめ、メーキャップ化粧品の種類や使い方、専門家によるおすすめするの化粧品などもお届けします。
-

悩み別講座
シミ、そばかす、しわ、たるみ、ニキビ,いぼ…あらゆる肌の悩みを、ドクター監修の読みやすい記事で解説。こんな時どうすればいい?という疑問にお応えします。
-

用語集
もっと効果的なスキンケアを実践したい!もっと若々しいエイジングケアをしたい!と思っている方へ。知っておくと便利な美容用語から、化粧品に含まれる成分、肌トラブルなどの症状についてのワードを解説していきます。
-
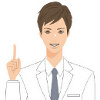
男の美容講座
美肌になりたい男性は注目!キレイな肌になりたいけど、どうやってスキンケアをするのか?男性でもわかるように、お肌に関する基本的な知識から、スキンケア、改善方法まで…ドクター監修の記事で解説していきます。
-

美容医療
「本当に悩みは解決できる?」「副作用はないの?」など、気になる美容医療の現状について、取材を基に詳しく解説します。
-

肌タイプ別講座
脂性肌、乾燥肌、混合肌、敏感肌、それぞれの肌質と正しいスキンケアをドクター監修の読みやすい記事で解説します。あなたに合ったスキンケア方法が見つかります。



